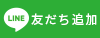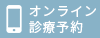THE RELATIONSHIP BETWEEN ORAL CARE AND SYSTEMIC DISEASES口腔内ケアと全身疾患との関連性について
最近、腸内環境、腸内フローラについての重要性が指摘されるようになり、腸活に励まれている方が増えてきております。
当院の外来でも、腸活についての質問を受けることが多くなってきました。
腸内環境を整えていくことはとても大事なことだと思います。然しながら、私たちの体にはいわゆる悪玉菌とくくられてしまう、体に対して悪影響を与える細菌が常在菌として存在しているのも事実です。
今回、口腔内に存在している歯周病菌と全身疾患について簡単にまとめてみました。敵を知ることで、ご自身の健康を維持するための対策を練ることが出来ます。
皆様の予防的ケアに対して少しでもお役に立てればと思います。
歯周病菌と循環器疾患との関連
21世紀初頭から歯周病菌と循環器疾患との関連性が認められるとの研究成果が発表されるようになって来ました。
歯周病菌により歯茎の炎症や骨の破壊を引き起こしてきます。炎症が強くなることで歯周病菌が血管内に入り込み、歯周病菌が産生する内毒素や歯周病の部位においてマクロファージという免疫細胞から産生される炎症性物質(TNF-α炎症性サイトカイン)が原因となって血管の内皮細胞に炎症を引き起こします。この結果血管内皮にコレステロールの沈着が促進され、動脈硬化が加速し、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞などの循環器疾患や、女性では低体重児早産のリスクが高まります。
院長のひとり言
この発表がされた頃の個人的な感想なのですが…
もう、今から20年近く昔の話です。
当時は大学病院で大腸外科医として頑張っていました。大学病院なので、大腸癌の患者様で糖尿病を合併している患者様は、糖尿病自体のコントロールが良くない方々が多く入院されていました。糖尿病の3大合併症(神経障害・網膜障害・腎症)を少なからず引き起こされている患者様です。
更に糖尿病により免疫力にも障害が出ている方をみておりましたので 『歯周病がそこまで酷くなるには糖尿病などの免疫力に影響が出る基礎疾患があるからなのでは?免疫力に影響が出る程のコントロールが悪い糖尿病だと、当然高脂血症も併発しているので、動脈硬化もそれなりに進行しているはずなので、歯周病菌による影響は2次的な物なのでは?』などと考えていました。
その後更に研究が進み、慢性的な歯周病を持つ方の心血管系リスクは歯周病の無い方と比較して約2倍程度に跳ね上がることも分かってきました。
歯周病菌と腸内フローラの関連
近年の研究に伴い口腔内の状態が腸内フローラにも影響を与えることが示唆されてきています。
歯周病菌が口腔内から消化管を通り抜け腸内に定着をすることにより腸内フローラのバランスを崩す原因となり得ると考えられています。
歯周病菌の一部(ジンジバリス菌:Porphyromonas gingivalis)は白血球などの免疫細胞の機能を低下させるジンジパインという蛋白分解酵素を分泌し、炎症性因子を作り出します。腸内で炎症が起こることにより、腸のバリア機能が低下し、腸管内での悪玉菌が増殖し易くなる可能性が示唆されています。
腸内フローラの多様性が失われることにより、消化機能、免疫機能の低下、全身性の慢性的な炎症性疾患や生活習慣病のリスクが高まる可能性も指摘されています。
腸内の免疫機能が弱まることにより、腸炎、過敏性腸症候群、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)のリスクが高まる可能性があります。
また、炎症性腸疾患は大腸癌のリスクファクターとしてとても重要な因子です。
また、腸内環境の悪化に伴い腸脳相関を通じ、精神的な健康や免疫機能に影響を及ぼすこともあります
院長のひとり言
腸内フローラの多様性、バランスなどについては、現在研究が盛んに行われています。
腸内細菌が我々の生活習慣や疾病、考え方など様々な影響を与える可能性が示唆されています。
自分自身、腸内フローラと各種疾患との関係性についての新しい知見の講義を聴くたびに、毎回驚きを隠せません。炎症性腸疾患や大腸癌などのリスクだけでは無く、先に述べた動脈硬化や高血圧、更に肥満や糖尿病、アトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患、うつ症状や不安障害、注意欠乏多動症や自閉スペクトラム症、肝疾患などに影響を与えている可能性が示唆されています。まるで地球という一つの生き物の上で、我々人類や多種多様な生物が存在し、その生物の生活史や活動により地球上の環境を左右させてしまう事と類似した様な状況なのか?などと想像を巡らせてしまいます。
腸内フローラを整えるためには、繊維質と発酵食品の積極的な摂取が推奨されています。
歯周病菌と癌の関連
歯周病菌の一部は口腔癌や食道癌との関連性が強く示唆されています。
また、大腸癌の発癌に関しても別な歯周病菌の関与が疑われています。多くの研究で大腸癌の腫瘍中に高頻度である種の歯周病菌が検出されていることが分かっています。現在、この歯周病菌が発癌の引き金となる可能性や、癌の成長や進行にも関与している可能性が示唆されています。
最近この歯周病菌が胃癌や膵臓癌の中にも検出されることが分かり、直接大腸とは関係の無い臓器の癌の発癌にも関与している可能性まで示唆されています。胃癌はヘリコバクターピロリ菌という細菌が原因ということが分かってきています。歯周病が進行しますとピロリ菌の同族であるキャンピロバクター(Campylobacter)やフソバクテリウム(Fusobacterium)という細菌が歯周ポケットに増えてきます。この歯周病菌達が食事の際、胃に入ることで胃潰瘍・胃がんが誘発されると考えられています。
ヘリコバクターピロリが胃の中に持続的に感染することにより、胃酸の酸性度が中性に傾きます。このため、本来は胃酸(塩酸です)により死滅するはずの歯周病菌が死滅せず腸管内に導かれてしまい、大腸癌などの発癌の原因となる可能性も指摘されています。
また、強い制酸剤を長期に内服することで、ピロリ菌が胃内に存在しているのと同様に胃内の環境が中性化され、歯周病菌が死滅せずに腸管内に到達する可能性がある事も最近のトピックスとなっています。
簡単にまとめますと、歯周病菌に伴う炎症そのもの、また歯周病菌が発生する酵素や毒素が細胞のDNAを損傷し、発癌に関与すると考えられているようです。また、一部の歯周病菌は免疫系の働きを抑制することで、腫瘍細胞に対する免疫が低下し、癌の増殖に影響を与える可能性があります。
院長のひとり言
にわとりが先なのか?卵が先なのか?と同じで、歯周病ありきで発症している病気なのか?そもそも病気があり、その影響で歯周病が発症しているのか?という疑問点は残ります。
然しながら、現段階ではどちらか片方だけよりも両方を合併されている方、歯周病のある方の疾患リスクが高いことを考慮していくと、口腔内ケアの大切さが伺い知れます。
歯周病の予防として
- 3ヶ月に1回程度の歯科受診及び歯石やプラークの除去
- 正しい歯磨き習慣
- 禁煙
- バランスの良い食生活
などが上げられます
当クリニックの概念として、CPC=総合的な予防的ケアを掲げています。
皆様の近隣でお仕事をされている歯科の先生方をご紹介させて頂きます。
どの先生も、今回の患者様への啓蒙活動に快くご賛同頂けた先生方です。
また、今回のお知らせの監修もお願いいたしました。
監修
- 小俣歯科医院
大和市南林間1-3-9
中村好子 先生
- 武内歯科医院
横浜市磯子区森1-11-4
武内清隆 先生
- 新山下デンタルクリニック
横浜市中区新山下1-5-6
小久保友子 先生
歯周病のケアを行い、様々な疾患リスクの低減に努めていきましょう。